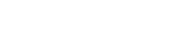「発達障害」それは未来を創る「特殊能力」だ
子供の才能は、無限の可能性を秘めています。しかし、社会の「普通」という枠組みから少しはみ出してしまうだけで、その可能性は「障害」という言葉でくくられてしまうことがあります。いわゆる「発達障害」と呼ばれる子供たち、彼らは本当に「障害」を持っているのでしょうか?私は、彼らこそが、未来を創る「特殊能力者」だと考えています。
偏見が生む「障害」という言葉
私自身、幼少期は集団行動が苦手で、勉強も得意ではありませんでした。しかし、特定の分野では卓越した能力を発揮できたと自負しています。高校では卓球の才能を伸ばし、それが自信となり、その後の人生を切り拓くきっかけとなりました。
この経験から感じるのは、社会が「発達障害」という言葉に持つ偏見の目です。集中力がないと見なされる人たちが、並外れた集中力を持つ人たちを「障害」と呼ぶ。それは、自分たちとは異なる才能を恐れ、理解できないがゆえのレッテル貼りではないでしょうか。
イーロン・マスク氏も、既存の学校教育を「洗脳教育」と批判しています。特定の分野に深く没頭し、他のことに興味を持たないという姿勢は、大人になれば「研究者」や「開発者」として尊敬される才能です。それが子供の頃は「発達障害」と呼ばれる。これは、能力を否定する差別にほかなりません。
「障害」ではなく「特殊能力」と呼ぶべき理由
経済が発展するためには、研究や開発が不可欠です。そして、その担い手となるのは、専門分野に特化できる才能を持った人たちです。彼らは、目の前の課題に深く集中し、常識にとらわれない発想で新しい価値を生み出します。
まさに、この「常識にとらわれない」という点が、発達障害と呼ばれる人たちの強みです。彼らは、多くの人が当たり前だと思っていることに疑問を持ち、新しい視点から物事を捉えることができます。これは、イノベーションを起こす上で欠かせない資質です。
身体的な障害を持つ人が、家族にとって生きる希望であるように、「発達障害」と呼ばれる子供たちも、社会にとってかけがえのない存在です。彼らの才能を「障害」と見なして人生を狭めるのではなく、「特殊能力」として最大限に引き出す環境を、社会全体で創っていくべきです。
才能を伸ばすための環境づくり
現状の特別支援クラスは、才能を伸ばすための手厚い教育が行われているとは言えません。むしろ、社会から切り離し、差別を助長する場となっているのではないでしょうか。
本当に必要なのは、子供一人ひとりの特性を理解し、その才能を伸ばすことに特化した教育です。得意なことにはとことん集中させ、苦手なことは無理にやらせない。集団行動が苦手なら、無理に人と合わせるのではなく、少人数で深い学びができる場を提供したり、専門家とつながる機会を増やしたりする。そうした柔軟な教育こそが、未来の科学者や開発者を育てる道だと信じています。
「発達障害」という言葉は、子供の可能性を摘み取ってしまう危険な言葉です。私たちは、この言葉を「特殊能力」と言い換えるべきです。子供の個性を尊重し、才能を伸ばすための環境を整えること。それが、この国を、そしてこの世界をより良くしていくための第一歩だと強く思います。
お子さんが「発達障害」と診断されて悩んでいる方へ。それは決して、絶望ではありません。むしろ、お子さんが特別な才能を持っている証拠だと、誇りを持ってください。そして、周りの言葉に惑わされず、お子さんの可能性を信じてあげてください。